2025年秋から放送されるNHKの連続テレビ小説「ばけばけ」。このドラマは、明治時代の作家である小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻、小泉セツをモデルにした物語です。日本の急速な西洋化と、取り残された人々の思いを描きながら、怪談話を愛した夫婦の姿を描いています。このドラマのタイトル「ばけばけ」には、どんな意味が込められているのでしょうか?本記事では、ドラマの背景やタイトルの元ネタ、そして見どころを紹介します。
物語のあらすじ
「ばけばけ」は、明治時代の松江を舞台に、松野トキという少女の成長を描いた物語です。松野家は上級士族の家系でしたが、時代の変化とともに家計は困窮し、トキは極貧の生活を送ることになります。そんな中、彼女は外国人英語教師の家で住み込みの女中として働くことを決意します。英語教師はギリシャ出身のアイルランド人で、過去に多くの苦しみを経験し、世界中を転々とした末に日本にたどり着いた人物です。
トキとその外国人教師は、初めは文化や言葉の壁に悩まされますが、やがてお互いの苦しみを理解し、心が通じ合っていきます。特に、二人は怪談話を好んで語り合う仲となり、奇妙な人々に囲まれたへんてこな暮らしが続きます。この「化ける」ような物語が展開する中で、トキは「この世をうらめしい」と思いながらも、次第に世界の美しさに気づいていくのです。
タイトル「ばけばけ」に込めた思い
タイトル「ばけばけ」は、急速に近代化が進む明治時代の日本の社会や価値観が「化けて」いく様子を象徴しています。この時代の変化に取り残された人々の思いが怪談という形で語り継がれていく中で、主人公トキの世界も、次第に「化けて」素晴らしいものに変わっていくのです。
また、タイトルの「ばけばけ」は、怪談や幽霊のイメージを連想させるとともに、物語の中で登場人物がそれぞれの心情や境遇を乗り越えて成長する様子を暗示しているとも言えます。この「化ける」テーマは、ドラマ全体を通して描かれる重要な要素であり、視聴者がどのように物語の中で心が変わり、成長していくのかが見どころの一つです。
小泉セツとラフカディオ・ハーンの実際の歴史
本作のヒロインである小泉セツは、実際の人物で、松江藩家臣の家に生まれました。彼女は、家計の困窮を助けるために幼い頃から働き、最終的にはラフカディオ・ハーン(後の小泉八雲)と結婚し、国際結婚を果たしました。小泉セツは、夫の怪談や民間伝承を再話するなど、日本の文化を世界に伝える役割を果たしました。
セツは、夫と共に明治時代の急速な西洋化の中で、名も無き人々の心の物語を語り継いだ存在です。その姿は、ドラマの中でどのように描かれるのか注目されています。
ドラマの魅力と期待
2025年秋に放送される「ばけばけ」では、ヒロインを演じるのは俳優の高石あかりさんです。高石さんは、これまで映画やドラマに出演しており、今回の役柄で朝ドラデビューを果たします。会見での意気込みを語った高石さんは、「見てくださる皆さんに温かい気持ちになってもらえる作品になるよう頑張ります」と話しており、視聴者への期待感が高まります。
また、舞台となる松江や熊本の美しい風景や、明治時代の社会背景もドラマの魅力の一つです。急速に西洋化が進む中で、伝統と新しい価値観が交錯する時代背景において、主人公たちがどのように成長していくのかがドラマの見どころとなるでしょう。
キャスト一覧:相関図
髙石あかり|松野トキ(主人公)
民話や怪談が大好きな松野家の一人娘。母・フミの作るしじみ汁が大好物。周囲から変わり者と見られるが家族思い。
岡部たかし|松野司之介(トキの父)
明治時代に収入を失った元上級武士。家族のために奮闘する不器用な父親。
ヘブン役(トキの夫・小泉八雲モデル)
国内外1767人の応募者の中からオーディションで決定。日本語は勉強中だが、ハーンのエッセンスを演技で表現。
池脇千鶴|松野フミ(トキの母)
民話や怪談に詳しいしっかり者の母。家族を優しく見守る。
小日向文世|松野勘右衛門(トキの祖父)
幕末を生き抜いた武士。剣では負けない自負があるが孫・トキには甘い。
吉沢亮|錦織友一(英語教師)
松江随一の秀才で、ヘブンをサポート。トキとも奇妙な縁で関わる。
北川景子|雨清水タエ
松江随一の名家に生まれた女性。トキに礼儀作法や教養を教える。
堤真一|雨清水傳
松江藩の上級武士。没落士族を助ける人格者。
板垣李光人|雨清水三之丞
雨清水家の三男で居場所を求め、トキたちの仕事場に入り浸る。
寛一郎|山根銀二郎
トキのお見合い相手。極貧生活で育つが武士の生き方を貫く。
さとうほなみ|なみ
農家出身で遊女となるが明るくたくましい女性。トキを気にかける。
丸井わん|野津サワ
元下級武士の娘でトキの幼なじみ。教師を志しトキを支える親友。
まとめ
NHKの朝ドラ「ばけばけ」は、明治時代の急速な西洋化と、取り残された人々の心の葛藤を描いた作品です。タイトルの「ばけばけ」には、物語の中で人々や世界が「化けて」いくテーマが込められています。また、ヒロインを演じる高石あかりさんの演技にも注目が集まっており、視聴者はこのドラマでどんな物語が展開されるのか、楽しみにしています。ドラマの放送が始まる前に、その背景やタイトルの意味を知っておくと、より一層ドラマを楽しむことができるでしょう。
関連記事
朝ドラ『ばけばけ』はつまらない? 先入観を超える面白さと見どころを徹底考察

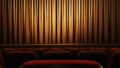

コメント