こんにちは!今日は『鬼滅の刃』に登場する童磨(どうま)というキャラクターについて、心理学の視点からゆるく深掘りしてみようと思います。
童磨は鬼の中でもかなり怖い存在で、やっていることもとてもひどいです。もちろん、彼の鬼としての行為や人を傷つける行動は絶対に許されるものではありません。でも、彼のキャラクターをただ「悪い奴」とだけ片付けてしまうのはもったいないくらい、いろんな心の問題や複雑さが詰まっています。
今回は、そんな童磨の心の内側や、彼と胡蝶忍(こちょうしのぶ)の関係を、心理学のキーワードを使ってわかりやすく解説していきますね。
簡単あらすじ
「鬼滅の刃」に登場する上弦の弐・童磨(どうま)は、初登場から異様な明るさと軽い口調で、人を喰う鬼とは思えない雰囲気を持っています。
しかしその裏側には、感情をほとんど持たず、人間の生死に何の感慨も抱かない冷徹さがあります。
彼は「万世極楽教」という宗教団体の教祖として多くの信者を集めながら、その信者を“救い”と称して喰らい続けてきました。
胡蝶しのぶの姉・胡蝶カナエを殺した張本人であり、しのぶにとっては復讐の相手です。
物語では、上弦集結後の戦いで胡蝶しのぶと対峙。
その後、栗花落カナヲと嘴平伊之助との共闘でついに倒されます。
最期は地獄に落ち、そこで初めて自分が本当は愛されていたことに気づく──そんな皮肉な結末を迎えます。
鬼になった理由:感情の欠落と認知の歪み

童磨は生まれつき「感情を持たない子ども」でした。
両親は信者から“神の子”と崇められる立場にあり、彼もまた特別な存在として育てられます。
しかし、本人はこう言い切ります。
「俺ね、悲しいとか寂しいとか、よくわかんないんだよ」
心理学でいう**「認知の歪み」**が、ここで既に始まっています。
本当は愛情を受けていたはずなのに、それを感じ取る心の受け皿がない。
結果として「自分は愛されない」という前提で世界を見てしまうのです。
自己肯定感の低下:価値の空虚さ
愛されている実感を得られないと、「自分には価値がある」という感覚も薄れます。
童磨の場合はそれが極端で、自己肯定感はほぼゼロのまま成長しました。
「人間って弱くて、可哀想で、だから食べて救ってあげるのが一番優しいんだよ」
この“優しさ”は完全に歪んでいますが、本人に悪意の自覚はありません。
心理学的には**「自己正当化」**と呼ばれる防衛機制が働いており、罪悪感を感じないよう自分に都合のいい理屈で塗り固めています。
歪んだ家族愛と条件付きの承認
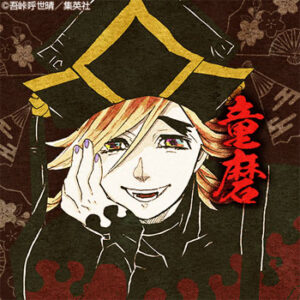
父は女性関係のもつれで信者を裏切り、母は毒をあおって命を絶ちます。
その混乱の中で、童磨は人間への信頼も完全に失いました。
「母さんが笑ってくれるなら、それでいいんだ」
これは心理学でいう**「条件付き承認」**です。
「何かをしたときだけ認められる」という愛情は、子どもにとって大きなストレスになり、歪んだ人間関係パターンを作ります。
防衛的攻撃性:笑顔の仮面
童磨の軽薄な笑顔は、感情を守るための仮面です。
「泣いたり怒ったりって、面倒くさいじゃん?だったら笑ってた方がいい」
この**「防衛的攻撃性」**は、他人との距離を一定に保ち、自分が傷つかないようにするための手段です。
表面的には朗らかですが、内面は常に冷え切っていました。
胡蝶しのぶとの戦い
胡蝶しのぶは姉・カナエを殺した童磨に対し、怒りと憎しみを胸に立ち向かいます。
しかししのぶの体格や腕力では、童磨の首を斬ることは不可能。
そこで彼女は藤の花の毒を体内に蓄えるという捨て身の作戦を選びます。
戦いの最中、童磨はしのぶに興味を示します。
「君さ、なんか可愛いね。あ、顔じゃなくて心がさ」
その言葉は皮肉でありつつも、童磨の中でしのぶが特別な存在になっていたことを示唆しています。
心理学的には**「鏡映し効果」**──相手の中に自分が持っていないものを見出し、惹かれる現象です。
しのぶは最後まで笑顔を崩さず、姉の思いと共に自らを毒として童磨に喰わせました。
最後のシーン:地獄での気づき
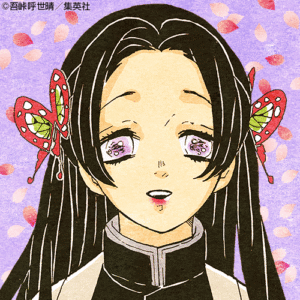
カナヲと伊之助の連携により、童磨はついに頸を落とされます。
死後、彼がたどり着いたのは地獄。
そこで再会したのは、かつて殺した胡蝶カナエでした。
「あれ?俺、もしかして……君のこと、好きだったのかな」
その瞬間、童磨は初めて“愛”に似た感情を抱きます。
しかしそれは、もう取り返しがつかない場所での気づきでした。
心理学的には、これは**「遅延された感情認知」**です。
長年感情を閉ざしていた人間(あるいは鬼)が、極限状態や死後にようやく感情を認識することがあります。
ただし、この気づきは生前の行動を帳消しにはしません。
まとめ
童磨は、生まれつきの感情の欠落と歪んだ環境によって、「愛を感じられない人間」として成長しました。
その結果、愛や救いを与えるつもりで、人を喰うという最悪の形で他者と関わりました。
本記事での心理学的分析は、あくまで彼の行動や心情を理解するためのものであり、決して鬼としての行為を正当化するものではありません。
それでも、彼の最後の瞬間に芽生えたわずかな感情は、どこか切なくもあります。
『鬼滅の刃』は、ただのバトル漫画ではなく、人間の心の闇や光を描いているからこそ、多くの人に響く作品なのだと改めて感じました。
これからも、こうしたキャラクターの深い部分に注目しながら楽しんでいきたいですね!
上弦の鬼の過去と心理をもっと知りたい方はこちら
鬼の特徴と登場編をまとめました。過去や心理をもっと知りたい方は各リンクからチェック!
| 位階 | 名前 | 能力・血鬼術 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 上弦の壱 | 黒死牟(こくしぼう) | 月の呼吸(剣技系の血鬼術) | 元・鬼殺隊の剣士で、霞柱・時透無一郎の先祖。六眼と6本の腕を持つ。 |
| 上弦の弐 | 童磨(どうま) | 冷気・氷を操る血鬼術 | 宗教団体の教祖。感情が希薄で常に笑顔。胡蝶しのぶと因縁がある。 |
| 上弦の参 | 猗窩座(あかざ) | 破壊殺(格闘術) | 武術に特化。強さを何より重んじる。煉獄杏寿郎と激闘を繰り広げた。 |
| 上弦の肆 | 半天狗(はんてんぐ) | 分裂と感情体の操縦 | 怯えの感情から分裂し、複数の分身体を戦わせる。無惨に忠実。 |
| 上弦の伍 | 玉壺(ぎょっこ) | 壺を使い水棲生物を操る血鬼術 | 壺から異形の魚や生物を生み出す。芸術に執着。 |
| 上弦の陸 | 堕姫(だき)&妓夫太郎(ぎゅうたろう) | 帯の操作(堕姫)、毒を含む血鎌(妓夫太郎) | 遊郭に潜んでいた兄妹鬼。二人一組で「上弦の陸」とされる。 |


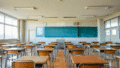
コメント